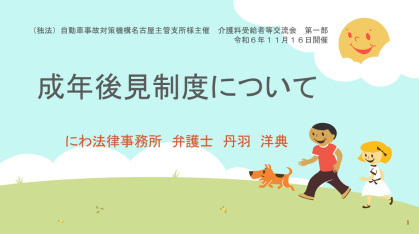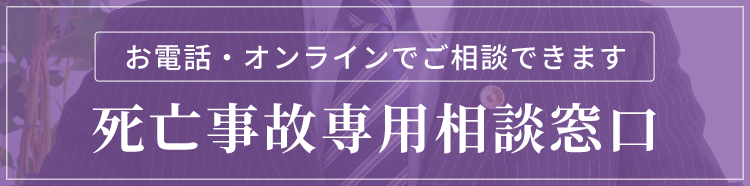当事務所について
(独法)自動車事故対策機構(ナスバ)名古屋主管支所様主催「介護料受給者等交流会」で、「成年後見制度について」と題する講演を行いました。
自動車事故対策機構様では、交通事故により重度の介護が必要になった方に対し介護料を支給されていますが(詳しくはこちらをご覧ください。)、介護料を受給されている方やそのご家族に対し、毎年交流会を実施されています。
本年度は令和6年11月16日に実施されましたが、弁護士丹羽はその第1部として「成年後見制度について」と題し講演を行いました。
交通事故で重傷頭部外傷を負い高次脳機能障害を生じた場合、被害者の方は認知判断能力を失い、単独で法律行為をする能力である行為能力を失ってしまうことが良く見られます。
その場合、成年後見制度を利用しないと、民事裁判を起こすことや不動産を処分したり、相続人として遺産分割等ができなくなります。
また、死亡事故で相続が生じ、相続人に認知症の方がいた場合などでも問題になります。
そのため、交通事故被害に遭った場合成年後見申立てを行わなければならない場面に多々遭遇します。
そこで、この講演では、交通事故被害者という観点から、成年後見制度や申立ての方法、実情などを詳しく説明し、多額の保険金が入った場合に利用される後見制度支援信託や、最近注目されている新しい制度である家族信託などについても説明いたしました。
後見制度を利用されているご親族のご不満の高さについて
その後の質疑応答では、実際に後見制度を利用されているご家族から、被後見人のための財産利用に不当な制限をかける専門職後見人の職務内容や、高い報酬、書類の作成を丸投げされるなどの不満や使い勝手の悪さ、後見人の変更が可能かなど、後見制度に対する不満が多数寄せられ、成年後見制度の利用勝手の悪さを改めて実感しました。
後見を申し立てても、最近では親族が後見人に選任されるケースは少なく、8割以上のケースで弁護士や司法書士などの親族以外の専門職後見人が選任されています(令和5年度81.9% R6.4厚生労働省「成年後見制度の現状」こちら)
そもそも成年後見制度が、判断能力を失った方の財産を守る制度ですので、家庭裁判所から選任された専門職後見人は、財産管理や身上監護がご親族のためではなく被後見人の利益となるかのみで判断します。
そのため、ご親族と専門職後見人の判断が相反し、専門職後見人の判断にご親族が不満を持つことが多々見られます。
他方、専門職後見人としても、裁判所からの指摘を過度に恐れ、ご親族らの実情を顧みることなく、必要以上に財産支出に消極的なケースも散見されます。
後見人の職務内容に不満がある場合は、選任者である管轄の家庭裁判所に直接相談してください。
判断能力が低下した方やそのご親族にとって、たとえ使い勝手が非常に悪くご親族に多大な負担をかけるとしても、一定の場面で成年後見制度の利用は強制されますので、その運用を担う家庭裁判所としても、実際の業務にあたる専門職後見人としても、利用者の声に真摯に耳を傾け、被後見人やそのご親族にとって柔軟なより使い勝手の良い制度に洗練されていくことを期待しています。
当事務所について
- 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。
- 名古屋市内の特定法律事務所依頼中の方の無料相談お断りについてです
- (独法)自動車事故対策機構(ナスバ)名古屋主管支所様主催「介護料受給者等交流会」で、「成年後見制度について」と題する講演を行いました。
- 人と車のテクノロジー展2024YOKOHAMAに参加(共同展示)しています
- 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。
- 令和5年7月5日 EDR及びCDR業務の中止、並びに、CDRアナリスト・テクニシャン資格をすべて返上しました。
- 令和5年6月の当事務所の新規相談枠の削減・停止についてです
- (公財)東海交通遺児を励ます会『第55回交通遺児を励ます大会』に出席いたしました。
- 令和3年9月までの全解決実績を更新しました
- 当事務所の全解決実績を更新いたしました
- ソニー損害保険株式会社、SBI損害保険株式会社の弁護士費用特約(弁護士費用保険)の取扱い停止について
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
-
損保ジャパン名古屋保険金サービス第二課担当者による、兼業家事従事者(専従者)の休業損害に関する主張について
NEW -
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。
NEW -
左橈骨近位端骨折後の左肘部痛事前認定非該当につき、異議申立てにより第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です。
NEW -
右股関節脱臼骨折後の可動域制限異議申立て第12級7号認定につき、紛争処理申請により第10級11号が認定された事案のご紹介です。
NEW -
名古屋市内の特定法律事務所依頼中の方の無料相談お断りについてです
-
国民共済coopの度重なる回答遅延について(顛末記あります)
-
子どもや若年独身者の死亡慰謝料の基準を見直すべきです
-
㈱光文社様「FLASH」年末年始特大合併号(令和6年12月24日発売)記事掲載
-
ドライブレコーダー映像・音声データの改ざんについて
-
相談センターの示談あっ旋と紛セの和解あっ旋の違いについて